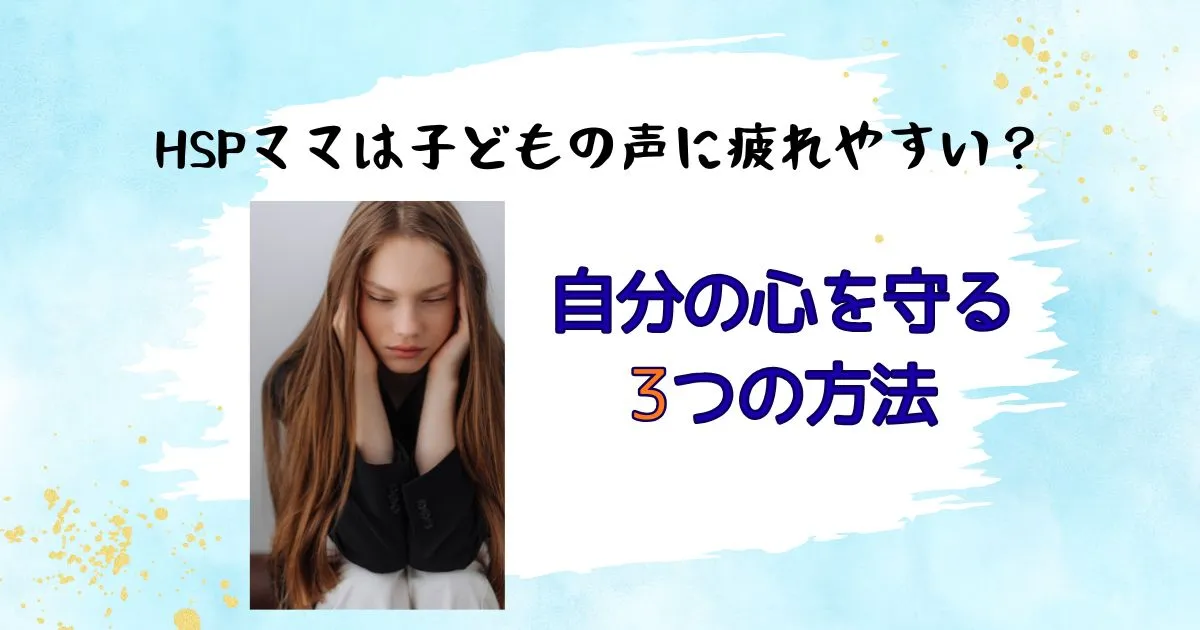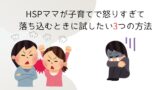「自分の子どもの声なのに、ずっと聞いていると疲れる」
「子どもの声で気が狂いそうになるなんて母親としておかしいのかな」
そんな自分に、罪悪感を抱いたことはありませんか?

私も可愛い我が子の泣き声や騒ぐ声をずっと聞いているとグッタリ疲れてしまうことがあります。
子どもの声で疲れてしまうのは、HSP(繊細さん)ならではの反応なんです。
あなたが「母親としておかしい」わけでも、「我慢が足りない」わけでもありません。
この記事では、HSPママが子どもの声に疲れやすい理由と心を守る3つの工夫を私の体験も交えてご紹介します。
最後まで読むと、HSPママが自分を責めずに穏やかに子どもと向き合えるようになります。
- HSPで子どもの声に疲れてしまう人
- 心を守る工夫や他のHSPママの体験談を知りたい人
HSPママが子どもの声に疲れやすい理由

HSPは五感がとても敏感で、特に音に反応しやすいタイプの人が多いといわれます。
そのため日常の生活音や子どもの声に刺激を受けやすく、他の人よりも早く音の疲れを感じてしまうことがあります。
HSPとは、生まれつき刺激や感情に敏感な気質を持つ人のことを指します。
心理学的には「外部からの情報を深く処理し、感受性が高い人」と定義されており、
日本でも多くの専門家が研究を進めています。(参考:HSP研究者エレイン・アーロン博士公式サイト)
HSPの詳しい性質については、こちらの記事でも紹介していますので、参考にしてくださいね。
子どもの泣き声や騒ぎ声が続くと、たとえ自分の子どもであっても気が狂いそうになりますよね。

私は外出先で子どもがワガママを言って暴れたとき、泣き声、騒ぎ声だけでも疲れるのに周りの目も気になってグッタリします、、、。
イヤイヤ期は一日中子どもが泣いて騒ぐのでHSPママにはしんどいですよね。
イヤイヤ期を乗り越える方法については、こちらの記事も読んでくださいね。
「子どもの声に疲れるなんて」と思うかもしれませんが、それは感受性が豊かで、まわりの変化にすぐ気づけるあなたの特性です。
HSPママは音だけでなく、子どもの表情や気持ちにも敏感に反応します。
だからこそ、子育ての中でストレスを感じやすいのも自然なことなんです。
子どもの声に疲れてしまうのは母親としておかしいわけではない

HSPママが子どもの声に疲れてしまうのは、決して母親としておかしいわけではありません。
HSPママは、子どもの声や雰囲気、感情にまで敏感に反応します。
泣き声や喧嘩の声を聞くと、心までざわざわしてしまうのも無理はありません。
私も夕方の忙しい時間に娘が「ねぇねぇママ、今日ね学校で○○ちゃんが、、、」とずっとお喋りしていたり、鼻歌を歌いながら宿題をやって、集中できていないとイライラしてしまいます。

また娘が休憩のときに観ているYouTubeの甲高いアニメの声や動画の音も、全部拾ってしまって頭がその音で一杯になります。
そのたびに「もっと余裕のあるママになりたいのに、こんなことでイライラするなんて」と落ち込んでしまうんですよね。
HSPママが子育てで怒りすぎて落ち込むときに試したい方法については、こちらの記事でも紹介していますので、読んでみてください。
でもHSPという気質を知ってから「私は疲れやすいだけで、娘を愛していないわけじゃない」ということに気づきました。
毎日ずっと同じ空間で子どもの声を聞いていると、誰だって疲れてしまいます。
HSPさんの場合はその疲れが少し早く来るだけ。
何もおかしいことではないのです。
HSPママが子どもの声に疲れるときに心を守る3つの工夫

HSPママが子どもの声に疲れるときに、心を守るためにできる工夫は以下の3つです。
- 子どもが元気に遊んでいる時間は、数分だけ別室に移動して深呼吸する
- 「ママ、ちょっと疲れちゃったから休みたいな」と伝えてみる
- 子どもが寝たあとに静かな時間を確保して、心をリセットする
1つずつ見ていきましょう。
子どもが元気に遊んでいる時間は、数分だけ別室に移動して深呼吸する
子どもが一人遊びに夢中になっていたり、テレビを観ている時間に数分でもいいのでトイレなど別室に移動して深呼吸してみましょう。
少しの時間でも自分だけの空間にいるだけで心がラクになります。

私も娘のイヤイヤの対応で辛くなると、少し長めにトイレにこもって気持ちを切り替えていました。
HSPママは責任感の強い方が多いので、「ずっと子どもを見てて対応してあげなきゃ」と心が張り詰めてしまっています。
でもほんの数分でも自分だけの空間で心を落ち着かせる時間を持つだけでも心の緊張が和らぐのでラクになれますよ。
「ママ、ちょっと疲れちゃたから休みたいな」と伝えてみる
一日中子どもの相手をしていて疲れてしまったときは正直に子どもに「休みたいな」と伝えてみてもいいですね。
意外と子どもが理解して静かにしてくれることもあります。
私も娘が夏休みでずっと家で遊びや話の相手をして、疲れたときに「ちょっとママ疲れたから休みたいな」と娘に伝えてみました。
すると「いいよ、休んで。塗り絵してるね」と言って私に毛布をかけてくれました。
もちろん毎回うまくいくわけではないし、兄弟がいるとなかなか静かにしてくれないこともあるでしょう。
それでも「大好きなママが疲れている」と知ったら「助けてあげよう」という気持ちになってくれる可能性も高いです。

ママだって疲れたら休んでもいいんですよ。
子どもが寝たあとに静かな時間を確保して、心をリセットする
子どもが寝たあとに静かな時間を確保して心をリセットしましょう。
HSPさんは一人の時間に好きなことをしたり頭の中を整理する時間があることで落ち着きます。
私も娘が寝たあとは、お酒を飲みながらバラエティ番組を観てストレスを和らげています。
寝る前には「Upmind」というマインドフルネスアプリで5分間、瞑想をしています。
「Upmind」はスマホのカメラに30秒指を当てるだけで自律神経のバランスを解析してくれたり、瞑想やヨガなどの音声、動画で心を整えることのできるアプリです。

お試しでやるなら無料会員でも十分だと思います。私も無料会員です。
1か月寝る前に5分の瞑想を続けていますが、前よりも心が穏やかになったように感じています。
少しでも心をリセットする時間があるだけで、「よし明日も頑張ろう」と思えるんですよね。
まとめ 自分を責めないで音ストレスを減らす工夫をしよう
HSPママが子どもの声に疲れてしまうのは、音や感情に敏感な気質を持っているからです。
でもそれは、あなたが冷たいからでも、母親失格だからでもありません。
むしろ、人よりも繊細だからこそ、子どもの小さな変化にも気づけるのです。
「疲れる」というサインは、心が「少し休ませて」と言っているだけ。

自分を責めないでくださいね。
音の刺激を完全になくすことは難しくても、少しでも音ストレスを減らす工夫はできます。
小さな工夫でも、気持ちはぐっと楽になります。
大切なのは「我慢して乗り切ること」ではなく、疲れた自分に気づいて、少し休む勇気を持つことです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。