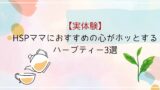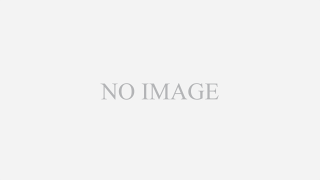「子どもが最近何するにもイヤイヤ言うようになった」
「一日中泣いて騒ぐしストレスも限界、、、」
「こんなにワガママなのは自分の育て方が間違っていたのかな」
子育ての最初の関門であるイヤイヤ期に疲れ果ててしまっているパパ、ママは多いですよね。
私もイヤイヤ期には悩まされました。
娘が1歳から3歳にかけては毎年何かしらの体調不良があり、、、。
円形脱毛症になったり椎間板ヘルニアになったり謎の発疹が体中にできることも。

それだけ心と体のストレスが限界まで来ていたのですよね。
永遠に続くような気がしてしまうイヤイヤ期ですが、必ず終わりは来ます。
そうは言っても毎日泣きわめく子どもと向き合っていると、育て方を間違えたのではないかと自信を無くしてしまうこともありますよね。
でも結論から言うとイヤイヤ期は子どもがちゃんと育っている証なのでパパ、ママは悲観的にならなくていいんです。自信を持ちましょう。
この記事ではイヤイヤ期がある理由や乗り越え方、ママ歴7年の私のおすすめの乗り越え方もご紹介します。
最後まで読むと自分だけじゃないんだと安心して、前向きにイヤイヤ期を乗り越えられるようになります。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
- 子どものイヤイヤ期に疲れ果ててしまった方
- イヤイヤ期を乗り越える方法や体験談を知りたい方
イヤイヤ期とは

イヤイヤ期とは、子どもに自我が芽生え、自己主張が強くなる時期のことです。
1歳半頃から始まり、ピークは2歳すぎ、3歳頃には落ち着いてきますが、個人差があります。
イヤイヤ期は自分でやるやる期
1歳過ぎて少しずつできることが増えてくると、「なんでもやってみたい!」と自分でやろうとするようになります。
自分でやろうとするなんて成長したなと微笑ましくなりますが、まだまだ手先も不器用でなかなかうまくいきません。
子どもは「やりたいのにうまくできない」葛藤から感情を爆発させてしまうのです。
毎日忙しい生活を送っているパパ、ママには「時間がないときにワガママ言って!」と感じてしまいますが、子どもが赤ちゃんから一人の人間として自立しようとしている大切な時期なのです。
脳の理性を司る部位が未発達
子どもが感情をコントロールできないのは、脳の理性を司る前頭前野という部位が未発達だからです。
なので「我慢できなくて当たり前」なのです。
子どもの脳の発達が追い付いてないから我慢ができないのだと知っているだけでもだいぶ気持ちが楽になりますよね。
脳が発達してくれば、感情をコントロールできるようになり、イヤイヤ期も落ち着いてくると言われています。

イヤイヤ期は赤ちゃんから一人の人間として自立しようと葛藤する時期なんですね!
イヤイヤする理由

ではなぜ子どもはイヤイヤ~!と感情が爆発してしまうのでしょうか。
以下の3つの理由があります。
- 自分でやりたいのにうまくできないから
- 空腹、眠いなど不快を言葉で伝えられないから
- パパ、ママの気を引きたいから
1つずつ見ていきましょう。
自分でやりたいのにうまくできないから
まず、身の回りのことを自分でやりたいのにうまくできないからです。
例えば以下のようなことですね。
- 洋服のボタンを自分で留めたい
- 靴下を自分で履きたい
- スプーンを使って自分でご飯が食べたい
- 買い物のカートを自分で押したい
余裕のあるときなら気長に待っていられますが、時間がなかったり、親の心の余裕がないときもありますよね。
私も娘がボタンを自分で留めたい!と言ったとき、娘がボタンを留めるのに夢中になっている間にさりげなく一番上と下のボタンは留めてしまっていました。
一番上と下は子どもには留めづらいんです。
でも自分で一つでも上手にボタンが留められたら、「すごいじゃん!」と大げさに褒めるようにしていました。

「自分でできた!」と思えれば子どもは満足するんですよね。
空腹、眠いなど不快を言葉で伝えられないから
子どもは空腹や眠いなど不快や思っていることを言葉でうまく伝えられません。
「うまくできなくて悔しい!」
「よくわからないけど疲れて眠い!」
ハッキリ伝えてくれれば親としては楽ですが、まだ伝えられないので、2歳前後の子どもでも言いやすい「イヤ」と言うことで「パパ、ママなんとかして!」と訴えているのです。
客観的に見れば、「しかたないよね」と微笑ましく思えますよね。
パパ、ママの気を引きたいから
わざとコップの水をこぼしたり、落書きをしたり、親の反応を見たくていたずらをすることがあります。
怒られることで自分に注目してほしいんですね。
親の過剰な反応を楽しんでいることもあります。
わざといたずらしているな、というときは冷静に「水をこぼされたらママ困るな」と伝えましょう。
やっていいこととダメなことの線引きが少しずつできるようになってきます。
また、普段からスキンシップをこまめにして、「いたずらしなくても、いつも見ているよ」と伝えることでわざと気を引くようなことはしなくなります。
イヤイヤ期の乗り越え方
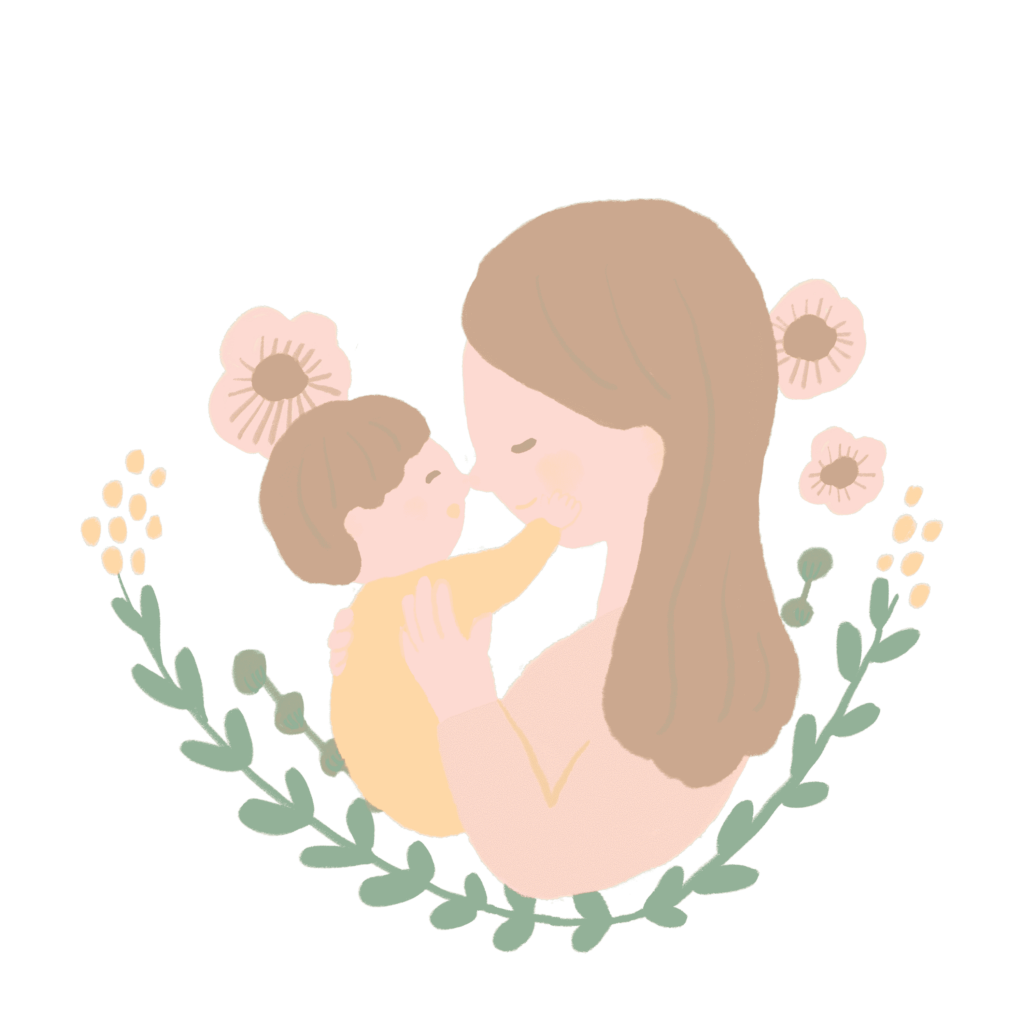
イヤイヤ期の乗り越え方は以下の3つです。
- 子どもの気持ちを受け入れつつ行動は制限
- 子どもに自分で選ばせる
- 気持ちを切り替えるタイミングをつくる
1つずつ見ていきましょう。
子どもの気持ちを受け入れつつ行動は制限
子どもの「やりたい!」気持ちを受け入れてあげるのは大切ですが人に迷惑をかけたり、危ないことは行動を制限する必要がありますよね。
私は娘を連れて買い物に行くとカートを押したがるので、やらせていました。
まだうまく操作できないので、さりげなく手を添えてカートを押させるのですが、「手で押さえないで!」と怒るんですよね。
でも「人にぶつかったら痛い思いさせちゃうから一緒にカート押させてね。やりたい気持ちはわかるけど、約束は守ろうね」と話すとしぶしぶ納得してくれたことがありました。
もちろんうまくいくことばかりではありませんが、やりたい気持ちを受け入れつつ、できないことは理由をちゃんと説明して約束を守らせましょう。
そしてちゃんと約束を守れたら「約束守ってくれてありがとう。助かったよ」など褒めることを忘れないようにしましょう。
子どもに自分で選ばせる
できる限り子どもに自分で選ばせてあげるようにしましょう。
なぜなら親から言われた通りにするのではなく、「自分で選べた」ことで自信につながるからです。
例えば「AとBのどっちの服にする?」など選択肢は2つにしておきましょう。
あまりたくさんの選択肢があると混乱してしまいます。
そしてどちらを選んでも困らないものにしましょう。
せっかく選んだのに「ダメ」と言われてしまったら余計に機嫌が悪くなってしまいます。
親が選んだものであっても「自分で決められた」ことが子どもの自己肯定感につながります。
子どもの自己肯定感を高めるために親ができる関わり方についてはこちらの記事で紹介していますので、読んでみてくださいね。
気持ちを切り替えるタイミングをつくる
子どもが癇癪を起こしているようなときは子どもの気持ちが落ち着くまで待つしかありません。
そして少し落ち着いてきたときに「おうちで一緒におやつ食べようか」
「ブランコ1回やったらおうちに帰ろうか」
など気持ちを切り替えるタイミングをつくります。

そうは言っても切り替えられないこともありますよね、、、。
私の娘の場合は公園で遊ぶと飽きることなく集中してしまうので、なかなか帰れませんでした。
少しだけ離れて様子を見てみても、お構いなし。
そのうち道路の縁石を歩き始めたり、道路に飛び出しそうで危なかったため、子どもを抱きかかえて強制退場することもありました。
子どもの性格によっては難しいこともありますが、根気よく親が気持ちを切り替えるサポートをすることで少しづつ自分でできるようになってきます。
イヤイヤ期の乗り越え方 ママ歴7年の私のおすすめ

私はママ歴7年になりますが、娘がイヤイヤ期のときは娘と真正面に向き合いすぎていたかもしれないと感じています。
娘は自我がだいぶ強いタイプで私はHSP。
HSPとは、生まれつき刺激や感情に敏感な気質を持つ人のことを指します。
心理学的には「外部からの情報を深く処理し、感受性が高い人」と定義されており、
日本でも多くの専門家が研究を進めています。(参考:HSP研究者エレイン・アーロン博士公式サイト)
家の中でも外でも大暴れする娘の泣き声に心底疲れ、家にいても虐待を疑われているのではないか、外でも人の目が気になって、心が落ち着くのは娘が寝たときだけ。

もう少し娘の気持ちを受け入れつつ受け流すようにしたほうがよかったのかなと感じています。
そんな中で私がイヤイヤ期にやって心が救われたおすすめの乗り越え方を以下の4つご紹介します。
- 子どものイヤイヤを動画に撮ってみる
- ネットで同じようなことで悩む人の体験談を読む
- 親に電話して話を聞いてもらう
- 子どもが寝た後はお酒とバラエティ番組で疲れを癒す
1つずつ見ていきましょう。
子どものイヤイヤを動画に撮ってみる

スーパーに行く途中の道路で地面にゴロンし始めた娘です。笑
「あ~もう無理!」と思ったときは、安全を確認したうえで、子どもの写真や動画を撮るのもおすすめです。
動画に撮っていると不思議と「この子は必死に何かを訴えているんだな」と客観的になれます。
そして撮った動画を「みてね」という家族で子どもの写真、動画を共有できるアプリにアップしていました。
イヤイヤで大暴れしている動画を見て、じいじやばあばが「大変だね、でも頑張ってる!」とコメントしてくれると励まされました。

時間が経ってから見返してみると笑える思い出になっています。
ネットで同じようなことで悩む人の体験談を読む
私がよく使っていたのはママ向け情報サイトの「ママリ」です。
少しでもわからないことがあれば「ママリ」で検索して同じようなことで悩む人の体験談を読んで参考にしていました。
「大変なのは自分だけじゃないんだ」と思えることで安心してまた頑張ることができました。
「こんなことママ友に聞いたら変に思われるかな」ということもネットなら聞きやすいこともありますよね。
また、「すくすく子育て」などの教育番組を観て、「子育てを頑張っている仲間がいる!」と思えたり、「わかる~!」と共感することでだいぶ心が救われました。
親に電話して話を聞いてもらう
私の娘のイヤイヤ期はちょうどコロナの時期だったため、支援センターに行けなくなってしまい、ママ友を作る機会もなくなってしまいました。
ママ友がいなくて不安な方にはこちらの記事もおすすめです。
学生時代の友達には結婚している人が少なく、みんな忙しいかなと遠慮して連絡を取ることも減り、旦那は平日は仕事で疲れてすぐ寝てしまうのでゆっくり話す時間もなく、、、。
実家は電車で片道2時間。気軽に行き来できる距離ではないので、たまに親に電話して話を聞いてもらっていました。
子どもが小さいときは宇宙人と一緒にいるような感覚になりますよね。
たまに「とにかく話の通じる大人と話したい!」となります。笑
モヤモヤした気持ちを親に話すことで頭が整理されて、「よく頑張ってるよ」と励ましてもらえるとまた頑張ろうと思えます。

イヤイヤ期の子どもと同じですね。笑
子どもが寝た後はお酒とバラエティ番組で疲れを癒す
私の娘はとにかくよく喋る子で、朝から晩までずっと喋ったり歌ったりしていました。
昼寝もしなかったので、唯一ホッとできるのは寝た後くらいでした、、、。
私はお酒を飲みながらバラエティ番組を観てリラックスするこの時間だけを目指して一日を乗り越えていました。
読書や音楽を聴くなど何でもいいので好きなことをする時間はやはり必要です。
また子どもと笑顔で向き合えるようにエネルギーをチャージしておきましょう。
ホッとする時間にハーブティーを飲んでみるのもおすすめです。
こちらの記事で紹介していますので、読んでみてくださいね。
まとめ 一人で抱えないで!イヤイヤ期を乗り越えよう

ここまでイヤイヤ期がある理由や乗り越え方、ママ歴7年の私のおすすめの乗り越え方をご紹介してきました。
イヤイヤ期はみんなが通る道。
いつか終わりが来る!

そうは言ってもしんどいものはしんどい!
めちゃくちゃ気持ちわかります。
でも変わらないように見えて毎日子どもは少しずつ成長しています。
子どもがワガママなわけでも親の育て方が悪いわけでもありません。
一人で抱え込まず、頼れる人には頼って、利用できるものは利用してなんとか乗り越えていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。