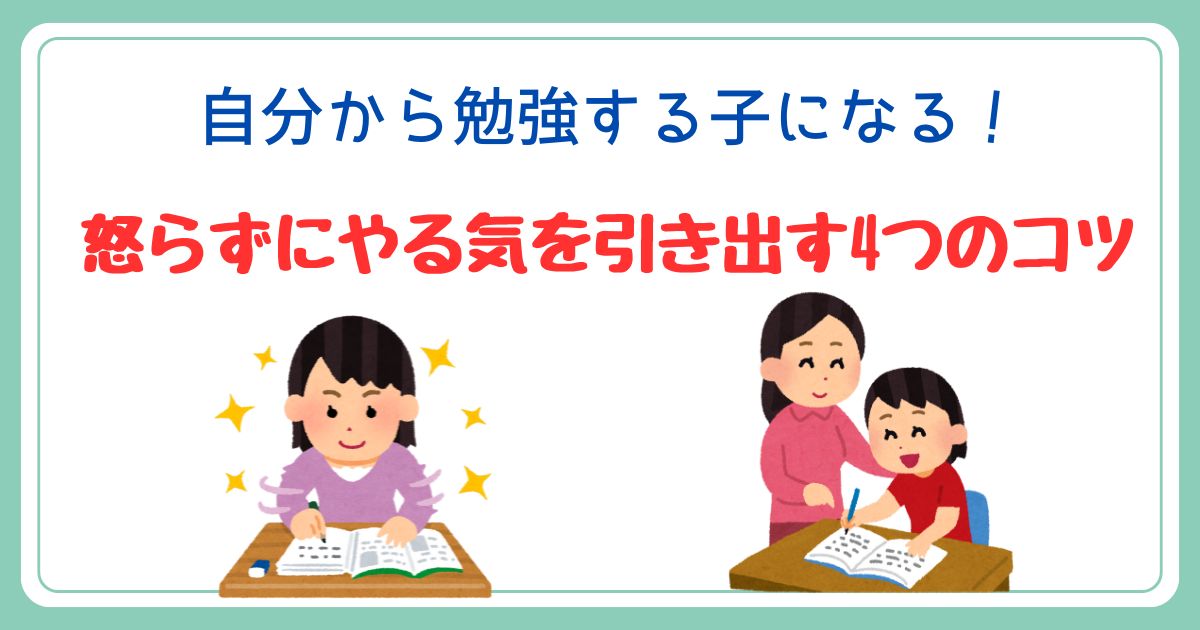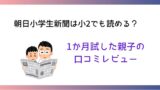小学生の子どもに毎日「勉強しなさい!」「宿題はやったの?」と注意して疲れてしまった、という保護者も多いでしょう。

自分から勉強してくれるようになったら、こんなに嬉しいことはないですよね。
私も小学1年生の女の子がいるので、毎日どうしたら勉強が好きになってくれるか試行錯誤中です。
小学生に自分で考える力をつけるために親ができることについては、こちらの記事にも詳しく紹介していますのでご覧ください。
この記事では小学生が自分から勉強するようになるために怒らずにやる気を引き出す4つのコツについて解説します。
この記事を読むと、子どもに毎日「勉強しなさい!」とガミガミ怒らなくて済むようになります。
- 小学生の子どもに毎日「勉強しなさい」と注意して疲れてしまった方
- 自分から勉強する子になるために親ができることを知りたい方
そもそも勉強って何のためにするの?

子どもから「勉強って何のためにするの?」と聞かれたらどう答えますか。
「将来困らないように」「いい会社に入るため」などと答えても子どもにはなかなか響きませんよね。
いろいろな答え方があると思いますが、私は「人生を豊かにするため」と考えます。
文字の読み書きができるから自分の意見を人に伝えられるし、読書を楽しむことができます。
英語が話せれば外国の方とコミュニケーションを取りやすくなります。
算数の知識を使って予算内で買い物をしたり、歴史や地理の知識を使って旅行をもっと楽しむこともできます。
勉強内容そのものは直接役に立たないことでも、例えば理科の実験のように仮説を立てて検証する、など物の考え方を学ぶことができます。
いろいろな価値観を知ることで、自分の世界を広げて、人間関係を広げたり、やりたいことを見つけることもできます。

大人になれば勉強の大切さを実感しますが、子どもにはまだ難しいかもしれません。
子どもが勉強する意味を聞いてきたときはチャンスと思って一緒に考えてみましょう。
「なるほど、勉強ってやったほうが自分のためになりそう」と思えば子どもは自然と勉強に興味を持つようになるでしょう。
自分から勉強する子の特徴
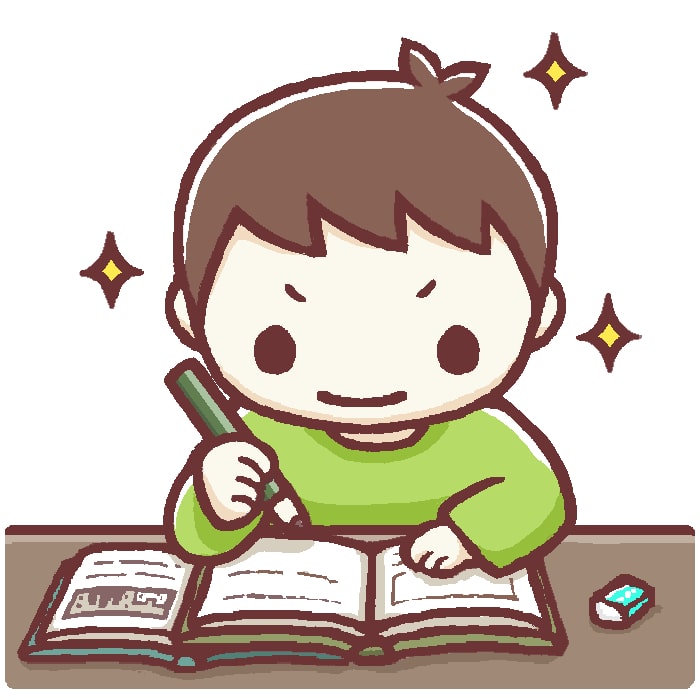
自分から勉強できる子には以下の3つの特徴があります。
- 親から勉強を強制されていない
- 自己肯定感が高い
- 勉強を習慣にできている
1つずつ見ていきましょう。
1.親から勉強を強制されていない
勉強は本来「させるもの」ではなく「自分からするもの」ですよね。
子ども自身が勉強にポジティブなイメージを持っていて、やったほうが自分のためになるとわかれば、勝手に自分から勉強するようになります。
そのために親は勉強を強制するのではなく、サポートするように心がけましょう。
2.自己肯定感が高い
自分から勉強ができる子は親から頑張ったプロセスを褒めてもらえた経験があることが多いです。
結果だけでなく、努力していることを親から認められ、応援してもらえると、子どもは「もっとやってみよう」と意欲が出てきます。
子どもの自己肯定感を高めるために親ができる関わり方についてはこちらの記事でも紹介していますので、読んでみてくださいね。
3.勉強を習慣にできている
幼少期から勉強をすることが毎日の当たり前になってしまえば、苦にならなくなります。
「夕食の前に宿題を済ませる」「学校に行く前にワークを3ページ進める」など時間を決めて毎日行います。
気分でやらない日が出てくるとだんだんやらなくなってしまうので毎日5分でも10分でも継続することが大切です。

娘は学校から帰って休憩したら、宿題とタブレット学習をしています。
自分から勉強する子になる!怒らずにやる気を引き出す4つのコツ

自分から勉強する子になるために怒らずにやる気を引き出すコツは以下の4つです。
- 子どもとの信頼関係を築く
- 勉強にポジティブなイメージを持たせる
- 集中しやすい環境を整える
- 結果だけでなく頑張ったプロセスを褒める
1つずつ見ていきましょう。
1.子どもとの信頼関係を築く
まず、子どもとの信頼関係をしっかり築いている必要があります。
普段から子どもの言うことを否定するのではなく、気持ちを受け止めてあげるように心がけましょう。
たとえば、子どもが「宿題やりたくない」と言ったとき「いいからやりなさい」と言うのと「やりたくない気持ちわかるよ」と言うのでは子どもの感じ方は変わります。
もちろん宿題はやらなければいけないので、気持ちと行動は分けて考えたほうが良いです。
でも、まず気持ちを受け止めてもらえるかどうかが子どもにとって大切です。
そうすることで子どもは親を信頼し、勉強のアドバイスにも耳を傾けるようになります。
2.勉強にポジティブなイメージを持たせる
学びとは本来楽しいものです。
なぜなら知らないことを知ることで価値観が広がり、できることが増えて自分の能力を高めることができるからです。
私自身も学生時代、勉強は「テストで良い点を取るため」にするもので、めんどくさい、苦痛なものだと思っていました。
しかし大学で教育の授業を受けたとき、「学びとは自分の世界を広げることができる楽しいものなのだ」と知って衝撃を受けました。
それからは学ぶことで知識が増えるのが楽しくなりました。
もっと早く気づいていれば学生時代の勉強にも意欲的に取り組めたかもしれません。
なので子どもにまず「勉強って楽しい」と気づかせることが大切です。

そのためには親が子どもと一緒に勉強を楽しんでみましょう!
3.集中しやすい環境を整える
いくら勉強に意欲的な子どもでも集中できる環境がなければ、意欲がなくなってしまいます。
集中しやすい環境は子どもによって違うので、静かなほうがいいのか、ある程度の雑音があるほうがいいのかは本人に聞いてみましょう。
また気が散る原因になるスマホやマンガは近くに置かず、わからないことをすぐ調べられるように辞書などを置いておきます。
また、親が子どもの勉強に関心を持ち、親自身も読書や資格の勉強など学んでいる姿を見せましょう。
そしてわからないことがあれば一緒に考えてあげましょう。

子どもにとって親が味方であると心強く、ますます意欲が出てきます!
4.結果だけでなく頑張ったプロセスを褒める
「疲れているのに頑張って宿題をやったね」「しっかり計画を立てて取り組めたね」など頑張ったプロセスを褒めましょう。
なぜなら結果だけを褒めてしまうと、子どもは「期待に応えなければ」とプレッシャーに感じてしまうからです。
「前回のテストは100点取れたけど、今回は80点だった。お母さんショック受けるだろうな」と考えて自信を失ってしまうかもしれません。
努力を認めてあげることで、「努力すれば良いことがあるんだ」と他のことも前向きに挑戦するようになるでしょう。
自分から勉強する子になるために我が家で心がけていること

私の娘は平日は宿題と進研ゼミのチャレンジタッチというタブレット教材をやっています。
休日は、進研ゼミのオプションで「自分で考えるワーク」という4教科の思考力を鍛えるワークを1日30分やっています。
チャレンジタッチが小学生の勉強習慣に役立つのか、についてはこちらの記事でも紹介していますので、読んでみてくださいね。
自分から勉強する子になるために我が家で心がけていることは以下の3つです。
- 何時から勉強を始めるかを自分で決めさせる
- こまめに褒める
- 勉強を一緒に楽しむ
1つずつ見ていきましょう。
1.何時から勉強を始めるかを自分で決めさせる
学校から帰ってきたら、近所の友達と1時間くらい遊び、おやつを食べて、少し休んだら宿題をやるという流れが多いです。
その際に何時になったら宿題をするかを自分で決めさせています。
最初の頃は決めた時間になってもなかなか切り替えられず、だらだらしていましたが、最近は切り替えられるようになってきました。
私が「〇時になったらやるんだよ」と決めるよりも自分で時間を決めたほうが「自分で決めたのだからしょうがない」と思うようです。

時間感覚も身についてきたようで、遊びと勉強のメリハリがつくようになってきました。
2.こまめに褒める
子どもの良いところはこまめに褒めるようにしましょう。
「できて当たり前」と思っていると褒めることが少なくなってしまいます。
私も最初はあまり褒めていなかったので、娘から「もっと褒めてよ!」と言われてしまったことがあります。
今は勉強の時間を守れたら「切り替えられたね!すごい!」と褒めたり「字が上手!丁寧でいいね」など良いところをこまめに褒めるようにしています。

褒められるとやっぱりやる気になりますよね!
3.勉強を一緒に楽しむ
こどもちゃれんじのワークの付録で理科の実験キットなどが付いてくることがありますが、一緒に楽しむようにしています。

改めて勉強すると意外と知らなかったことがあったりして楽しいですよ!
子どもは面白いことがあると「どうしてこうなるんだろう」「じゃあこうしてみたらどうだろう」と自分でどんどん調べていきます。
親も一緒に楽しんで勉強している姿を見せることで子どもはますます「勉強って楽しいものなんだ!」と思えます。
また子どもと一緒に社会について勉強するために朝日小学生新聞を試してみたレビューをこちらの記事で紹介していますので、読んでみてください。
まとめ 勉強は本当は楽しい!親も一緒に楽しもう
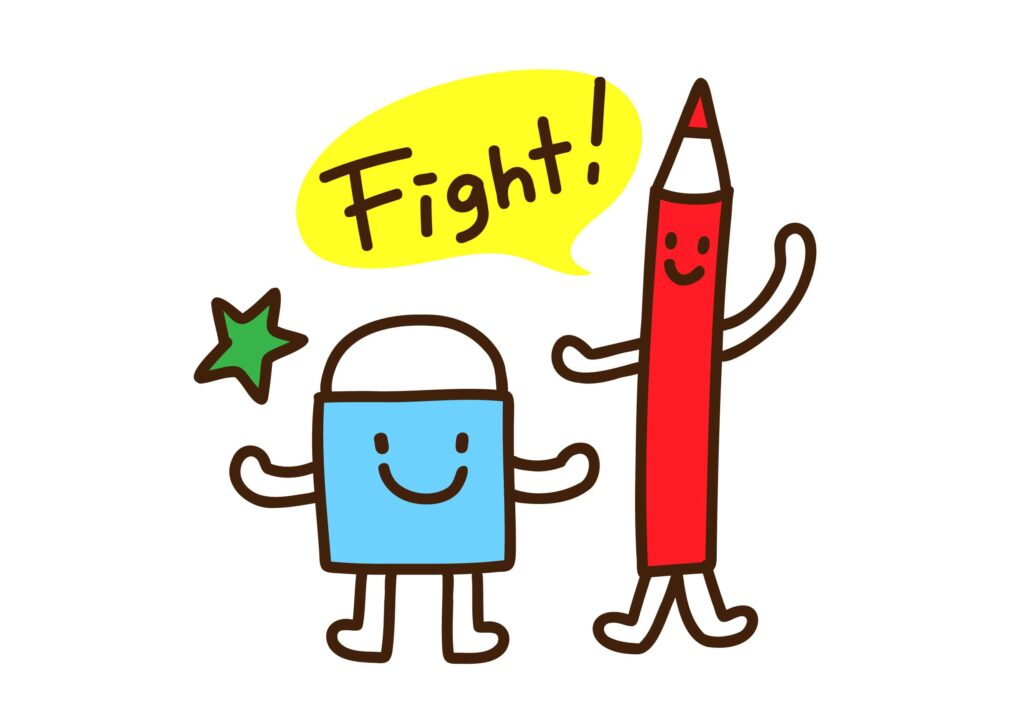
今回は小学生が自分から勉強する子になるために怒らずにやる気を引き出す4つのコツについて解説しました。
まず子どもとの信頼関係をしっかり築くことが大切です。
そして勉強を強制するのではなく、子どもが自分から勉強したくなるように学びの楽しさに気づかせてあげて、環境を整えてあげましょう。
結果だけでなく頑張ったプロセスを褒めてあげることも忘れてはいけません。
親も一緒に勉強を楽しむ姿を見せることで子どもの勉強へのイメージもポジティブに変わります。

一緒に勉強を楽しんでみましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。