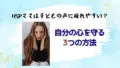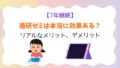「物を減らしたいのに、捨てられない」
「部屋が散らかると疲れるのに、片づけが進まない」
HSP(繊細気質)の人にとって、断捨離はかなりのエネルギーが必要な作業ですよね。
私自身も、もともと片づけや断捨離が得意ではありませんでした。
使っていない物でも手放すことが怖かったり、頂き物を捨てることに罪悪感を抱いたり、判断に時間がかかったり…。
「できない自分」が嫌になって、さらに動けなくなることもありました。
それでも、少しずつ部屋を整えていく中で気づいたことがあります。

HSPは片づけが苦手なのではなく、気持ちの整理に時間が必要なだけ。
この視点に立つと、断捨離は驚くほど楽になります。
この記事では、HSPが断捨離でつまずきやすい理由と、今日からできる小さな一歩を分かりやすくまとめました。
最後まで読むと「がんばれない日があっても大丈夫」と心が軽くなります。
- 断捨離が進まず疲れてしまうHSPさん
- HSPでも無理なくできる小さな一歩を知りたい人
HSPはなぜ物が多いと疲れやすいのか

HSPの脳は外から入る情報を深く処理するので、一般の人なら「なんとなく散らかってるな」程度の刺激も、HSPには強く響きやすい特徴があります。
さらに、視界に入る物が多いほど脳が同時に処理する情報が増え、疲れやすくなると言われています。

家の中が散らかっているだけでエネルギーが削られてしまうのですね。
HSPの詳しい性質については、こちらの記事を参考にしてください。
たとえば以下のような環境はHSPにとって常に通知音が鳴っている状態のように感じられます。
・視界にたくさんの物がある
・散らかった状態が続いている
・色や形がバラバラの物が置かれている
静かに過ごしているつもりでも、心の奥ではずっと情報を処理し続け、疲れが溜まりやすくなります。
我が家は娘が工作をするのが好きなので、気づくと娘の作品がリビングに増えがちです。
リビングがごちゃごちゃしてくると落ち着かず、家にいても休まらない感覚がありました。

「片づけたいのに動けない」という葛藤で自分を責めてしまった時期もあります。
けれど今思えば、それは“怠け”ではなく、気質の特性。
HSPの脳は、余計な刺激が少ない状態を心地よく感じます。
散らかった部屋で疲れてしまうのは、とても自然な反応なのです。
HSPが断捨離でつまずきやすい3つの理由
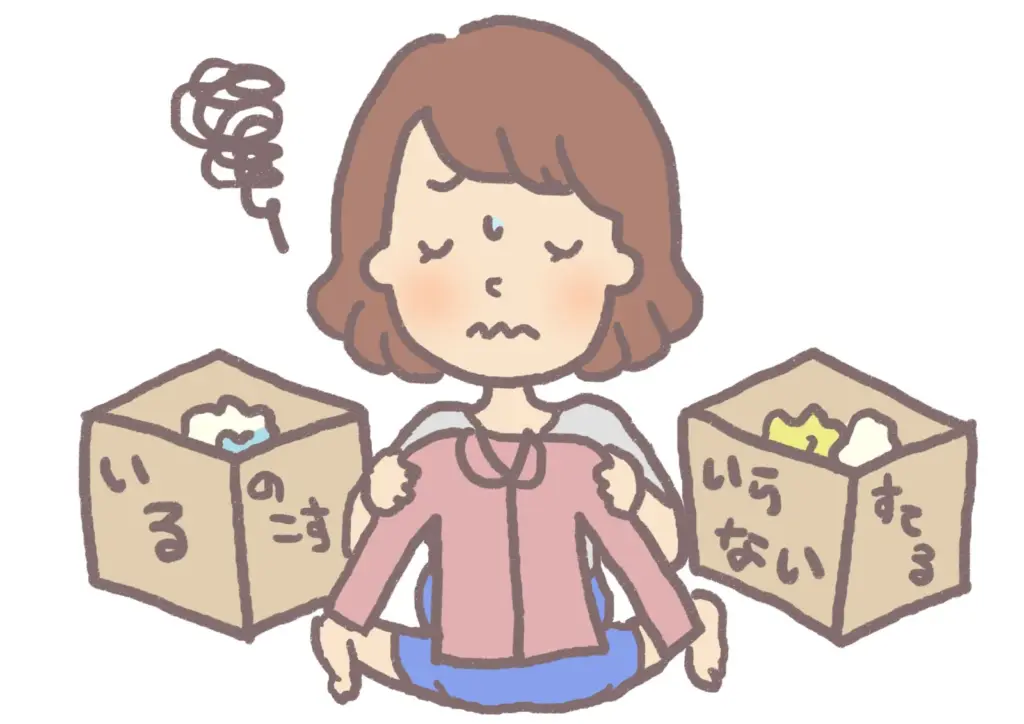
HSPが断捨離でつまずきやすい理由は以下の3つです。
- 捨てることに罪悪感を抱きやすい
- 迷う物が多く、決断疲れが起きる
- 思い出やストーリーが深く結びついている
1つずつ見ていきましょう。
捨てることに罪悪感を抱きやすい
HSPは以下のように物にも気持ちを乗せてしまいがちです。
「捨てたらかわいそう」
「頂いた人に申し訳ない」
「使わなくてごめんね」
そう感じた瞬間、心のブレーキが働きます。
不要とわかっていても、手放す決断が苦しくなるのはそのためです。
私もスーパーのパートで働いていたとき、同僚の娘さんが昔着ていた服を3着ほど頂いたのですが、なかなか捨てられずにいます。
私の娘に着させてあげてほしいという善意で譲ってくれたのですが、娘の好みの服ではありませんでした。

娘はこだわりが強いので気に入らないと絶対着ないんですよね、、、。
恐らく着ることはないのに捨てられないのは、物そのものよりも「気持ち」を捨てるような感覚があるのです。
迷う物が多く、決断疲れが起きる
HSPは「残すか手放すか」を判断に迷う物が多く、すぐに疲れてしまいます。
ひとつひとつの選択に対して以下のように丁寧に考えてしまうのです。
「これ、本当に使わない?」
「また必要になるかも」
「思い出があるし…」
このように頭の中で小さな会議が始まると、なかなか終わらないんですよね。
本棚を30分で片付けようと思っていたのに、本当に不要か中身を確認しながらやっていたら1時間以上かかり、疲れ切ってしまうこともありました。

買い物も考えすぎて疲れるのでメモに書いたもの以外はできるだけ見ないようにしています。
日々の家事をするのもHSPにとって疲れやすいですよね。
こちらの記事でも紹介していますので、読んでみてくださいね。
思い出やストーリーが深く結びついている
HSPは、物にまつわる思い出やストーリーが深く結びついています。
そのストーリーが鮮明に浮かぶため、手放すことで思い出を否定するように感じてしまうのです。
たとえば以下のような物の背景を思い出すことがあります。
- 買ったときの気持ち
- 使っていた時期の状況
- 一緒にいた人の顔
私も押し入れの片づけ中に、娘が赤ちゃんのときによく遊んでいたオモチャを見つけると、「こんな時期もあったなあ」と懐かしくなってしまい、未だに捨てられないでいます。
「赤ちゃんの頃は目が離せないし、夜泣きで寝不足になって大変だったな」とそのオモチャを使っていたときの思い出まで蘇ってくるんですよね。
でも大切な思い出は動画や写真に残しているし、記憶にしっかり残っているなら、物を手放しても大丈夫です。
ただどうしても取っておきたいのであれば無理して手放すことはありません。

気質によるものなので自分を責めなくていいですよ。
今日からできる「HSPにやさしい断捨離ステップ」

ここからは、私自身が「これなら続けられる」と実感した小さなステップを紹介します。
HSPが疲れにくく、心を守りながら進められる順番で負担が少ない方法です。
ステップ1 まずは視界のノイズだけ整える
最初は「一角だけ」「視界に入る場所だけ」でいいので整えましょう。
部屋全体をやろうとすると、ほぼ確実に途中で疲れます。
たとえば、以下のような「目に触れやすい場所」を整えるだけで心が軽くなります。
・机の上
・テレビ周り
・キッチンカウンター
・リビングの一部
私もダイニングテーブルの一角になんとなく置きがちな、郵便物や娘が描いたお絵かきの紙などを整理しただけで、気持ちのざわざわが少し落ち着きました。

視界に入る部分を少し整えるだけでも、刺激が減ってラクになりますよ。
ステップ2 迷う物は「とりあえずボックス」へ入れる
迷う物は無理に決めずに「とりあえずボックス」に入れましょう。
HSPにとって最も疲れるのは「残す? 捨てる?」の判断です。
私も娘がこどもちゃれんじで使っていた付録のオモチャやぬいぐるみなど、使わないかもしれないけど迷うものは、蓋つきの収納ボックスに入れています。
そして2、3か月程してから娘と一緒に必要かどうか確認して捨てます。

時間が経ってから娘に聞くと意外と熱が冷めて「もういらない」と言われることも多いです。
とりあえずボックスを作っただけで、断捨離のストレスが大きく減りました。
後で見返すと意外と「やっぱり使っていない」と冷静に判断できることも多いです。
決断を先送りするというより、心を守るための一時避難というイメージです。
ステップ3 いきなり捨てるのではなく「観察」から始める
いきなり捨てるのではなく「観察する」だけでOKと決めましょう。
HSPは「捨てるかどうか」の二択が重く感じやすいものです。
以下のように自分の心と向き合うと、捨てられない理由が少しずつ言語化され、物への執着が自然と薄れていきます。
・なぜ手放せないのか
・どんな気持ちが動いているのか
・本当に必要かどうか
私も娘が使っていたベビーカーやチャイルドシートをつい最近まで捨てられずにいました。
観察して自分の気持ちを整理すると、もう一人っ子にすると決めていたのに心のどこかで「本当に一人っ子でいいのだろうか」という迷いがあるとわかりました。
でも最近やっと「一人っ子でも大丈夫」と決心がついたので、手放すことにしたのです。

手放した後は何か自分の中で吹っ切れたような気持ちになりました。
HSPが一人っ子の子育てをするときに心を軽くする方法については、こちらの記事を参考にしてくださいね。
もちろん、観察しただけではすぐに物が減るわけではありません。
けれど、HSPにとって大切なのは「焦らず、自分のペースで納得して手放す」こと。
観察の時間は、考えすぎて動けない時間ではなく、心の準備を整える時間です。
このステップを丁寧に踏むことで、後になって迷わず決断できるようになります。
無理にスピードを求めず、心が「もう大丈夫」と感じたときに次へ進めば大丈夫です。
まとめ 断捨離が苦手でも大丈夫!HSPだからこそできる部屋づくり
断捨離は、物を減らすことが目的ではありません。
HSPにとって大切なのは、心が落ち着く空間を少しずつ育てること。
HSPは刺激に敏感だからこそ、自分が落ち着ける環境を作るセンスがあります。
以下のようなことは、すべて気質によるもので、あなたが悪いわけではありません。
・物が多いと疲れやすい
・罪悪感や決断疲れが起きやすい
・思い出と結びつきやすい
今日からできる小さな一歩は、机の上を5分整えることでも、迷う物をとりあえずボックスに入れることでもOK。
少しずつ進めれば、必ず心が軽くなっていきます。

できない日があって当然。あなたのペースで大丈夫です!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。