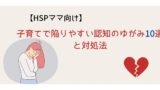「子どもの自己肯定感を高めたほうがいいと聞くけど、親はどう関わればいいんだろう」
「自己肯定感が低いとどうなるの?」
「親がやってはいけない関わり方ってあるの?」
なんとなく「自己肯定感が大事」と聞いたことはあっても、具体的にどうすればいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、子どもの自己肯定感とは何か、低いとどうなるのか、親がやりがちな自己肯定感を下げる関わり方と高める関わり方について私の体験を交えてご紹介します。
- 自己肯定感って聞いたことはあるけどよくわからない方
- 子どもの自己肯定感が低いとどうなるか知りたい方
- 子どもの自己肯定感を高めたい方

ぜひ最後までご覧ください。
自己肯定感とは?

自己肯定感とは「自分には価値がある」「自分は大切な存在だ」という、自分自身を肯定できる気持ちのことです。
他人との比較や結果だけで自分を判断するのではなく、自分自身の存在や努力を認められる心です。

良いところだけではなく、悪いところも含めてありのままの自分を認められることですね!
自己肯定感が高い子どもの特徴
自己肯定感が高い子どもには以下のような特徴があります。
- 新しいことに挑戦しやすい。失敗しても「またやってみよう」と前向きに思える。
- 友人関係で自分の意見をしっかり伝えられる。
- 周囲からの評価や意見に左右されすぎず、自分の価値観を持てる。

親としては自己肯定感の高い子に育ってほしいと思いますよね。
自己肯定感が低い子どもの特徴
自己肯定感が低い子どもは以下のような特徴があります。
- 「どうせ無理だ」「自分にはできない」と初めから諦めがち。
- 他人の評価に敏感で、人との比較で落ち込むことが多い。
- 褒められても素直に受け入れず、「ただ運がよかっただけ」と思ってしまう。

HSP気質のある私はまさにこれです。自分のようになってほしくないと思います、、、。
子どもの自己肯定感が低いとどうなる?

子どもの自己肯定感が低いと、心の健康や社会的な成長にさまざまなマイナスの影響があります。
自己肯定感は心の土台になるものなので、土台がしっかりしていないと生きづらさを感じてしまうのです。
子どもの自己肯定感が低いと以下のようになることがあります。
- 失敗を恐れて挑戦しなくなる
- 友達を批判したり嫉妬して意地悪をしてしまう
- 自分の軸がなく他者の評価を気にしてしまう
- 友達や恋人に依存する

親としては自分の子どもが自己肯定感が低いと心配になってしまいますよね。
他者の評価を気にすることなく自分軸で生きるとどんなメリットがあるのか、についてはこちらの記事でもご紹介していますので参考にしてください。
こども家庭庁による『我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査(令和5年度)』によると、「今の自分が好きだ」と答えた日本のこども、若者は53.4%なのに対して、欧米など他国では70%以上が同様の回答をしており、日本は比較的低めであることがわかっています。
このことから「自己肯定感が低いこと」は個人の問題だけでなく国全体の子どもの幸福や将来に関わる大きなテーマだと言えます。
親がやりがちな自己肯定感を下げる関わり

親がやりがちな自己肯定感を下げる関わり方は以下の3つです。
- 他の子と比べてしまう
- できないことを指摘しすぎる
- ネガティブな言葉を投げかける
1つずつ見ていきましょう。
他の子と比べてしまう
「○○くんはもっとできてたよ」という比較は、自分の価値を「他人と比べてどうか」という軸で考えさせてしまうため、自己肯定感を下げる要因になります。
兄弟の間で「お兄ちゃんはできてたのに、あなたはできない」などと比べてしまうのも子どもにとって大きな心のキズになってしまうので注意が必要です。

過去の子どもと比べてできるようになったことに目を向けてあげましょう!
できないことを指摘しすぎる
できていない部分ばかりに目を向けて注意することが続くと、子どもは「自分はダメな存在」だと思いやすくなります。
大人でも職場の上司に自分のできないことばかり指摘されたら、やる気を失いますよね。

「このくらいできて当たり前」と思わずに、少しでもできたことを認めてあげたいですね。
ネガティブな言葉を投げかける
「なんでこんな簡単なことを間違えるの?」「どうしていつもこうなの?」など否定的な言葉が繰り返されると、子ども自身が自分を否定する声を内側に持つようになります。
完璧主義な親は子どもが少しでもミスをするのが許せなくてネガティブな言葉を投げかけてしまいがちです。

子どもにとって親から言われる言葉の影響はとても大きいです。
子どもの自己肯定感を高める親の関わり方と声かけ
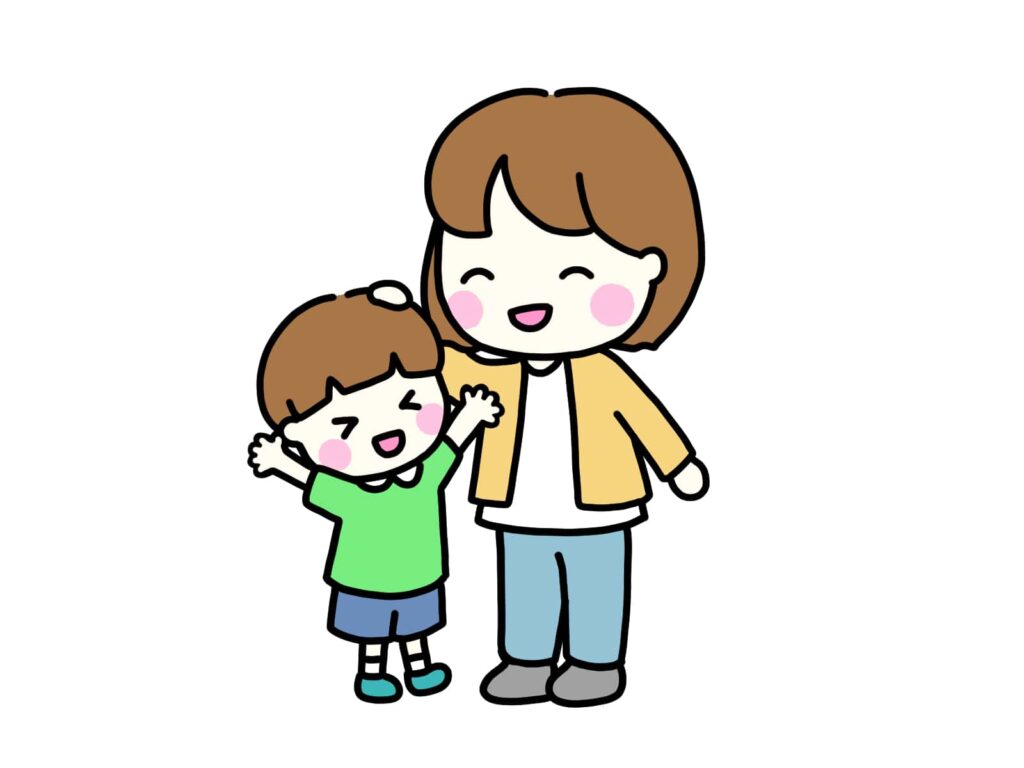
子どもの自己肯定感を高める親の関わり方の声かけについて以下の3つをご紹介します。
- 子どもの存在そのものを認める
- 結果だけでなく努力の過程を褒める
- 自分で選ばせる
- 小さいことでも感謝の言葉をかける
1つずつ見ていきましょう。
子どもの存在そのものを認める
「あなたがいてくれるだけで嬉しい」という気持ちを言葉にすることで、子どもは「自分は自分のままでいいんだ」と思えます。
忙しい毎日のなかでつい子どものできないところばかりが目について怒ってしまいがちですが、そんなときは、子どもが生まれた日のことを思い出してみましょう。

「この子が生まれてきてくれただけで嬉しい。」と思いましたよね。
「どんなことがあっても味方だよ」「大好きだよ」という声かけを日頃から心がけましょう。
子どもにとって親から存在を認められることほど安心できることはありません。
結果だけでなく努力の過程を褒める
テストで100点をとったら「100点がとれてすごいね」と褒めがちですが、「毎日疲れていても勉強頑張ってたもんね」と努力の過程を褒めるように気をつけましょう。
「100点をとらないと褒めてもらえない」と感じて、80点だと「こんな点数じゃガッカリさせてしまう」と自信を失くしてしまいます。
「失敗してもいいんだよ」「ちゃんと努力していたのを知ってるよ」と声かけすることで、子どもは「またやってみよう!」と思えます。
我が家では毎日チャレンジタッチをやっていますが、一日のレッスンをしっかりやったら必ず褒めるようにしています。
勉強習慣をつけさせるためにとても有効なのでこちらの記事も参考にしてみてください。
自分で選ばせる
「明日の服は何にする?」「何をして遊びたい?」など子どもに自分で選ばせるようにしましょう。
「自分のことは自分で決められるんだ」と思えることは自己肯定感を高めることにつながります。
私は娘が着る服について「こっちのほうがいいんじゃない?」「買った服はまんべんなく着てほしいからこっちも着てよ」と口出ししてしまったことがありました。
娘は「何で私が着る服をママに決められないといけないの?着るのは私でしょ」と言っていました。

娘の言うことは確かにもっともですよね。
それからは口出しはせずに自分で決めさせるように気をつけています。
娘はさらにオシャレになり、今では本を読んで可愛い髪型や服の研究をして楽しんでいます。
小さいことでも感謝の言葉をかける
子どもがお手伝いをしてくれたり気配りしてくれたら、小さいことでも「ありがとう。助かったよ」「気づいてくれて嬉しい」と感謝の言葉をかけましょう。
「自分は役に立てたんだ」と思えることも自己肯定感を高めることにつながります。
お仕事の体験を通して誰かの役に立つ経験をするにはキッザニアがとても良かったので、これから行く方はこちらの記事も参考にしてみてください。
私は娘が料理の手伝いをしてくれたとき、「手伝ってくれてありがとう。すごく助かったよ!」と言うと「ママが大変そうだから。手伝ってあげたいからやってるんだよ」と言ってくれました。

娘なりにママの役に立ちたいと思ってくれているようです。
「やって当たり前」と思わずに、こまめに感謝の言葉をかけてあげましょう。
【体験談】娘が全校生徒の前でピアノに挑戦!
私の娘は小学1年生のとき、年に1回ある学芸発表会でピアノに挑戦しました。
娘の通っている学校では、年に1回全校生徒1500人の前で、ピアノや歌、楽器の演奏などを披露したい人が発表する機会があります。

娘が「みんなの前でやりたい!」と言ってきたときは、驚きました。
ですが、やりたい人が全員できるわけではなく、1学年2人までと決められていて多い場合は抽選で決めるとのことでした。
抽選とはありますが、事前に1年生の前で発表する日もあったので、おそらく実力で発表者を選ぶのでしょう。
娘はピアノを習っておらず、「きらきら星」を弾きたいと一生懸命に練習していましたが、1年生の前で発表したときにピアノを習っている子の上手な演奏を聴いて自信を失くしているようでした。
そこで私は「もし選ばれなくても、抽選だからしょうがないね。でも、1500人の前でピアノを発表したいと立候補したこと自体がすごいことなんだよ。」「ママはいつも応援してるからね。」と娘に伝えました。
結局、先生たちの配慮で1年生は立候補した5人全員が発表できて、娘は緊張しながらもピアノの発表をやり遂げました。

娘はこの経験が自信になって「毎年立候補するんだ!」と言っています。
今年は2年生なので応募者が多い場合は落ちてしまう可能性もあるかもしれませんが、娘の挑戦する気持ちを大切にしたいです。
「もし失敗してしまっても、挑戦する勇気がすごい、いつでも応援しているよ」と伝えることで娘はまたやってみようという気持ちになれたのではないかと思います。
親自身の自己肯定感も大切
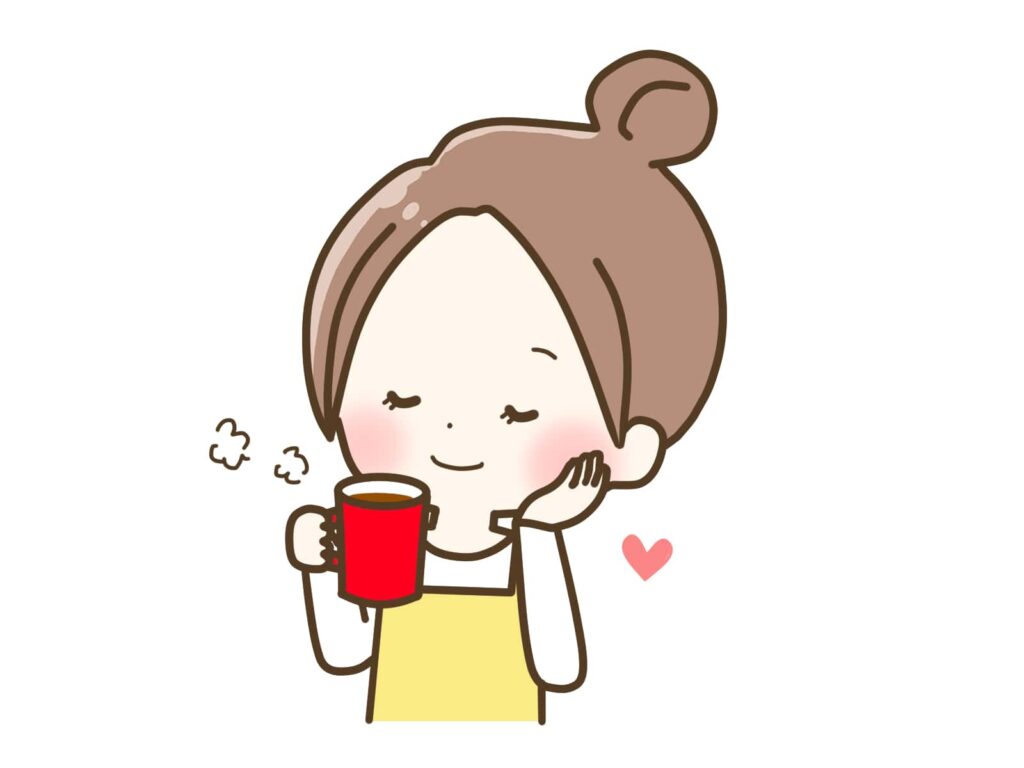
子どもの自己肯定感を高めるには、親の自己肯定感を高めることも大切です。
親が自分自身を大事にしていないと子どもにも伝わってしまいますよね。

私も自己肯定感を高めようと心がけているところです。
ここで、マザーテレサの名言をご紹介します。
「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから」
「言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから」
「行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから」
「習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから」
「性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから」

心に留めておきたい名言です。
「自分なんてダメだ」と思えば思うほど行動や習慣にもネガティブな影響を与えて、運命も悪い方向に変わってしまうのは怖いですよね。
ただ、子どもの自己肯定感に親の影響は確かに大きいですが、地域や学校でも自己肯定感を高める機会はたくさんあります。
過度にプレッシャーを感じず、親自身が「幸せになっていいんだ」と自分を認めてあげることが大切ですよね。
とくにHSPさんは認知のゆがみによって自分を責めてしまいがちですよね。
こちらの記事も参考にしてみてください。
まとめ 子どもと一緒に親の自己肯定感も高めよう
自己肯定感とは、良いところも悪いところも含めて、ありのままの自分を認めてあげられることです。
心の土台になる自己肯定感が低いと生きづらさを感じてしまうようになります。
親は子どものありのままを認めてあげて、子どもの挑戦を応援してあげましょう。
同時に親自身もありのままの自分を認めて子どもと一緒に自己肯定感を高めることが大切です。

親だって幸せになっていいんですよ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。